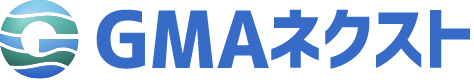所有者不明土地の問題を解決!新制度と相談先をプロが解説
所有している土地の隣が誰のものか分からなかったり、相続した土地の処分に困ったりしていませんか。近年、日本では所有者が分からない土地が増加し、社会問題となっています。土地の所有者が不明だとどうなるのか、土地の所有者がわからない場合はどうすればいいのか、不安に思う方も多いでしょう。
この問題に対処するため、国は特別措置法を施行し、所有者の探し方から土地の管理、処分に至るまで新たなルールを設けました。具体的には、法務局での手続きを通じて土地を適切に管理する所有者不明土地管理制度や、裁判所による管理命令といった仕組みが始まっています。
また、不要な土地を国に引き渡す国庫帰属という選択肢や、条件を満たせば所有者不明の土地を時効取得するにはどうすればよいか、あるいは逆にそのような土地を買いたい場合の手続きなど、様々な解決策が用意されました。しかし、各制度にはメリット・デメリットがあり、どの方法が最適か見極めるのは簡単ではありません。
この記事では、所有者不明土地に関するあらゆる疑問にお答えし、具体的な解決策と、失敗や後悔をしないためのポイントを専門家の視点から分かりやすく解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。
- 所有者不明土地を放置することで生じる具体的なリスク
- 土地の所有者や相続人を自分で調査するための基本的な方法
- 国が定めた所有者不明土地問題を解決するための各種制度の概要
- 各制度のメリット・デメリットと、最適な解決策の選び方
所有者不明土地の放置は危険!その問題点とは
- 土地の所有者が不明だとどうなる?
- 所有者の基本的な探し方を解説
- 法務局での登記情報の確認方法
- 土地の所有者がわからない場合はどうすればいい?
- 所有者不明の土地を時効取得するには?

土地の所有者が不明だとどうなる?
土地の所有者が不明な状態を放置すると、様々な問題が発生する可能性があります。個人の財産の問題にとどまらず、周辺地域や社会全体に悪影響を及ぼすことも少なくありません。
まず、土地の管理が適切に行われなくなります。雑草が生い茂って景観を損なったり、害虫が発生したりする衛生上の問題や、不法投棄の場所になるなど、周辺の生活環境の悪化を招くおそれがあります。建物が残っている場合には、老朽化による倒壊の危険性も高まり、近隣住民の安全を脅かすことにもなりかねません。
次に、土地の利活用が著しく困難になります。例えば、隣接する土地の所有者が、境界の確認や塀の設置、越境している木の枝の伐採などをしたくても、所有者と連絡が取れないため交渉や同意を得ることができません。また、地域開発や公共事業、災害復旧のための工事を進めようとしても、用地買収の交渉相手が分からないため、事業が停滞する原因となります。
これらのことから、所有者が不明な土地は、単に「持ち主が分からない土地」というだけでなく、地域の安全や発展を妨げる深刻なリスクをはらんでいると言えます。
所有者の基本的な探し方を解説
土地の所有者が分からない場合、まず取り組むべきは公的な記録をたどって調査することです。調査の第一歩は、対象となる土地の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することから始まります。
登記事項証明書は、その土地の所在地を管轄する法務局で誰でも取得可能です。証明書には、土地の所在、地番、面積といった物理的な状況のほか、現在の所有者(登記名義人)の氏名・住所などの権利に関する情報が記載されています。
もし、登記名義人が既に亡くなっている場合は、戸籍を遡る調査が必要になります。登記名義人の最後の住所地を基に、その市区町村役場で戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍などを取得します。そこから、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をたどり、配偶者や子の有無を確認していくことで、法律上の相続人を特定していきます。
相続人が複数いる場合や、代襲相続(子が先に亡くなっている場合に孫が相続人になること)が発生している場合は、調査が複雑になり、膨大な時間と手間がかかることもあります。

法務局での登記情報の確認方法
前述の通り、所有者調査の基本は法務局での情報収集です。法務局では、登記事項証明書の取得以外にも、所有者調査に役立つ制度が用意されています。
登記事項証明書は、法務局の窓口で申請するほか、郵送やオンラインの「登記・供託オンライン申請システム」を利用して請求することもできます。オンライン請求は手数料が安く、自宅やオフィスから手続きできるため便利です。
また、親族が所有している不動産がどこにあるか分からない場合、2026年2月から「所有不動産記録証明制度」が開始される予定です。この制度を使えば、特定の人物(相続人など)が名義人となっている不動産の一覧を証明書として取得できるようになり、調査の負担が大幅に軽減されると期待されています。
さらに、2024年4月1日から「相続人申告登記」という新しい制度も始まりました。これは、相続が発生した後、遺産分割協議がまとまらない場合でも、自分が相続人の一人であることを簡易に登記できる仕組みです。これにより、少なくとも相続関係者が誰であるかを公示でき、土地が完全に所有者不明となる事態を防ぐ効果があります。

土地の所有者がわからない場合はどうすればいい?
登記事項証明書や戸籍をたどる調査を行っても所有者が判明しない、あるいは判明しても連絡がつかない場合は、より専門的な対応が必要になります。
まず考えられるのは、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に調査を依頼することです。専門家は職務上の権限で住民票や戸籍の附票などを請求できるため、個人では追跡が難しい所有者の現在の所在を突き止められる可能性があります。
調査を尽くしてもなお所有者が見つからない場合は、後述する「所有者不明土地管理制度」の利用を検討することになります。これは、利害関係者の申立てにより、裁判所が所有者不明の土地の管理人を選任する制度です。選任された管理人は、土地の保存や管理、裁判所の許可を得て売却などの処分も行うことができます。
いずれにしても、自力での調査には限界があります。調査に行き詰まった段階で、早めに専門家へ相談することが、問題解決への近道となります。
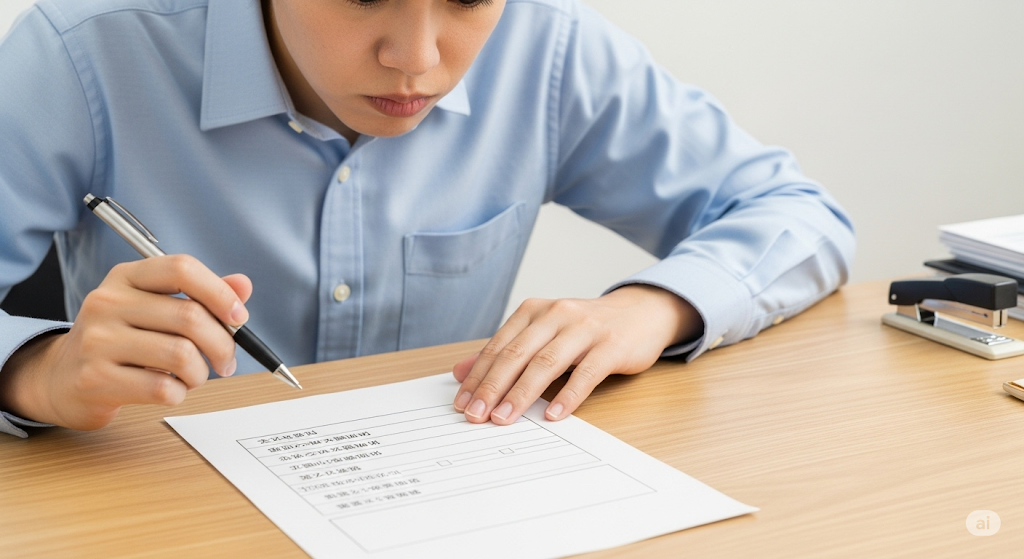
所有者不明の土地を時効取得するには?
長年にわたり他人の土地を自分の土地であると信じて利用してきた場合、その土地の所有権を時効によって取得できる可能性があります。これを「取得時効」と言います。
取得時効には2つの種類があります。
一つは、土地の占有を始めたときに、自分に所有権があると信じ、そう信じることに過失がなかった(善意無過失)場合です。このケースでは、10年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と土地の占見を続けることで時効が成立します。
もう一つは、占有開始時に他人の土地であることを知っていた(悪意)、または知らなかったことに過失があった場合です。この場合は、20年間の占有継続が必要となります。
ただし、時効取得のハードルは決して低くありません。「所有の意思をもって」という要件は、例えば土地の賃料を払っていたり、固定資産税を所有者の代わりに納付しているだけだったりすると、認められないことが多いです。あくまでも、自分の所有物として管理・利用している実態が客観的に証明できなくてはなりません。
時効が成立したとしても、自動的に所有権が移るわけではありません。登記上の所有者やその相続人に対して、所有権移転登記を請求する裁判を起こし、勝訴判決を得て初めて登記名義を自分に移すことができます。手続きが非常に複雑で法的な専門知識が不可欠なため、時効取得を検討する場合は必ず弁護士などの専門家に相談してください。

所有者不明土地問題を解決する国の新制度
- 所有者不明土地の特別措置法が施行
- 新設された所有者不明土地管理制度とは?
- 裁判所から出される管理命令の効力
- 不要な土地を手放せる国庫帰属制度
- 所有者不明の土地を買いたい場合の手続き
- 各制度のメリット・デメリットと所有者不明土地の専門家
所有者不明土地の特別措置法が施行
所有者不明土地問題の深刻化に対応するため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)」が制定されました。この法律は、所有者不明土地の発生を予防し、既に発生してしまった土地を円滑に利用・管理するための仕組みを定めています。
この法律の大きな柱の一つが、所有者不明土地を公共の利益のために活用しやすくする制度です。例えば、公園や集会所といった地域住民のためになる事業(地域福利増進事業)であれば、都道府県知事の裁定により、所有者の同意がなくても最長10年間の使用権を設定できるようになりました。
また、道路建設などの公共事業においては、従来よりも簡易な手続きで土地を収用できるようになり、事業の迅速化が図られています。
さらに、2024年4月1日からは、この法律の流れを汲む形で不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。これは、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料が科されるというものです。これにより、所有者不明土地の新たな発生を抑制することが期待されています。

新設された所有者不明土地管理制度とは?
2023年4月1日から、所有者不明土地の管理に特化した「所有者不明土地管理制度」が始まりました。これは、所有者不明土地問題の解決策として大きな役割を果たすことが期待される新しい制度です。
この制度の特徴は、従来の財産管理制度(不在者財産管理人や相続財産清算人)が対象者の財産全体を管理するのに対し、問題となっている特定の土地や建物のみを対象に管理人を選任できる点です。これにより、より迅速かつ効率的に問題解決を図ることが可能になりました。
利害関係人(例えば、隣地の所有者や、土地を買いたい事業者など)が地方裁判所に申し立てを行い、裁判所が管理の必要性を認めると、「所有者不明土地管理人」が選任されます。
選任された管理人は、その土地の保存・管理行為を行うほか、裁判所の許可を得ることで、土地を売却したり、建物を取り壊したりといった処分行為も行う権限を持ちます。この制度の活用により、これまで放置されてきた土地の適切な管理や、円滑な取引が実現できるようになります。
制度の比較:所有者不明土地管理制度と従来制度
| 制度名 | 対象財産 | 主な目的 | 管理人の権限(例) |
| 所有者不明土地管理制度 | 特定の所有者不明の土地・建物 | 対象不動産の適切な管理・処分 | ・保存、管理行為・売却、取壊し(要裁判所許可) |
| 不在者財産管理制度 | 所在不明者の全財産 | 不在者の財産全体の保護・管理 | ・全財産の管理<br>・遺産分割協議への参加(要裁判所許可) |
| 相続財産清算人制度 | 相続人が不明な被相続人の全財産 | 相続財産の清算・分配 | ・全財産の管理・換価・債権者への弁済、受遺者への遺贈 |
裁判所から出される管理命令の効力
「所有者不明土地管理制度」に基づき、裁判所が管理人を選任する決定のことを「所有者不明土地管理命令」と呼びます。この命令が発令されると、対象となる土地の管理処分権は、選任された管理人に専属することになります。
これは非常に強力な効力です。たとえ後から本来の所有者が現れたとしても、管理命令が出ている土地については、所有者自身が勝手に売却したり、賃貸したりすることはできません。管理や処分に関する一切の権限は、管理人が行使します。
この仕組みにより、土地の購入希望者や開発事業者は、安心して管理人と取引を進めることができます。取引の途中で本当の所有者を名乗る人物が現れて契約が無効になる、といったリスクがなくなるため、所有者不明土地の流動性を高める上で極めて重要な役割を果たします。
管理人が土地を売却するなどの処分行為を行う際は、事前に裁判所の許可を得る必要があります。裁判所は、売却価格が不当に安くないかなどを審査し、適正な取引が行われるよう監督します。
不要な土地を手放せる国庫帰属制度
相続したものの、利用価値がなく、売却も困難で、管理コストだけがかかる…。このような「負の資産」となりがちな土地が、所有者不明土地の予備軍となっています。こうした問題を解決するため、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
この制度は、相続または遺贈によって土地を取得した人が、一定の要件を満たす場合に、土地の所有権を国に引き渡すことができる仕組みです。
申請ができるのは、相続で土地を取得した個人に限られ、法人や売買で取得した人は対象外です。申請は、その土地を管轄する法務局に行います。申請後、法務局による審査が行われ、国に引き取ることができない土地(例えば、建物がある、土壌汚染がある、境界が不明確であるなど)に該当しないと判断されれば、承認されます。
承認された場合、申請者は負担金を納付する必要があります。この負担金は、その土地の管理に今後10年間で必要となる標準的な費用を考慮して算定されます。
負担金の算定例
| 土地の種目 | 負担金額 |
| 宅地 | 面積にかかわらず原則20万円(一部の市街地では面積に応じて算定) |
| 田、畑 | 面積にかかわらず原則20万円(農用地区域などでは面積に応じて算定) |
| 森林 | 面積に応じて算定 |
| その他(雑種地など) | 面積にかかわらず原則20万円 |
(注)詳細は法務省の資料をご確認ください。
この制度を利用することで、将来にわたる管理の負担や、次世代への負の遺産の継承を防ぐことができます。
所有者不明の土地を買いたい場合の手続き
所有者不明となっている土地であっても、購入を希望する事業者や個人にとっては魅力的な物件であるケースもあります。法改正により、以前よりは所有者不明土地を購入しやすくなりました。
最も一般的な方法は、前述の「所有者不明土地管理制度」を活用することです。土地の利害関係者として裁判所に管理人選任の申し立てを行い、選任された管理人から土地を購入します。管理人は裁判所の許可を得て売却を行うため、法的に安定した取引が可能です。
また、土地が複数の相続人の共有状態になっており、その一部の人の行方が分からない、というケースも多くあります。この場合、改正された民法の共有制度のルールが役立ちます。所在が不明な共有者がいる場合、残りの共有者は裁判所に申し立てることで、所在不明者の持分を取得したり、その持分を含めた不動産全体を第三者に譲渡したりすることが可能になりました。
いずれの方法も、裁判所での手続きが必須となり、法律の専門知識が求められます。所有者不明土地の購入を検討する場合は、まず弁護士や司法書士に相談し、どのような手続きが可能か、費用や期間はどれくらいかかるのかを十分に確認することが大切です。

各制度のメリット・デメリットと所有者不明土地の専門家
これまで解説してきたように、所有者不明土地問題に対処するための制度は複数用意されています。しかし、どの制度にもメリットとデメリットがあり、自身の状況に最適なものを選ぶ必要があります。
例えば、「時効取得」は費用をかけずに所有権を得られる可能性がありますが、要件が厳しく、裁判が必要になるなどハードルは非常に高いです。
「相続土地国庫帰属制度」は不要な土地を手放せる画期的な制度ですが、誰もが利用できるわけではなく、審査手数料や負担金といったコストがかかります。
「所有者不明土地管理制度」は管理や処分を円滑に進められますが、裁判所への申し立てや管理人の報酬など、こちらも相応の費用が必要です。
これらの法的な手続きを、法律の知識がない個人が進めることは極めて困難であり、かえって時間や費用を浪費してしまうリスクもあります。一つの手続きでうまくいかなかった場合に、別の角度からアプローチを試みるといった柔軟な対応も、専門家でなければ難しいのが実情です。
以上の点を踏まえると、所有者不明土地に関するお悩みを抱えた際は、問題を放置したり、一人で抱え込んだりするのではなく、速やかに専門家へ相談することが最も確実で安全な解決策と言えます。不動産の調査、法的な手続き、そして最終的な売却や管理までをワンストップでサポートできる専門家を見つけることが、問題解決の鍵となります。
- 所有者不明土地は管理不全により周辺環境の悪化を招く
- 公共事業や民間取引の妨げとなり経済活動を停滞させる
- 所有者調査の基本は法務局での登記事項証明書の取得
- 登記名義人が故人の場合は戸籍を遡る相続人調査が必要
- 自力での調査が困難な場合は専門家への依頼を検討する
- 取得時効は要件が厳しく裁判も必要なためハードルが高い
- 2024年4月から相続登記が義務化され違反すると過料の対象となる
- 所有者不明土地管理制度は特定の土地のみを対象に管理人を選任できる
- 選任された管理人は裁判所の許可を得て土地の売却も可能
- 相続土地国庫帰属制度により不要な土地を国に引き渡せる
- 国庫帰属制度の利用には審査があり負担金の納付も必要
- 所有者不明土地を購入したい場合は管理制度の活用などが考えられる
- 各制度にはメリットとデメリットがあり最適な選択は状況による
- 法的手続きは複雑で専門知識が不可欠なため個人での対応は困難
- 不動産と法律に精通した専門家への相談が最も確実な解決策となる