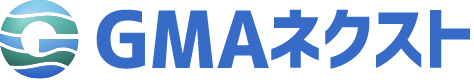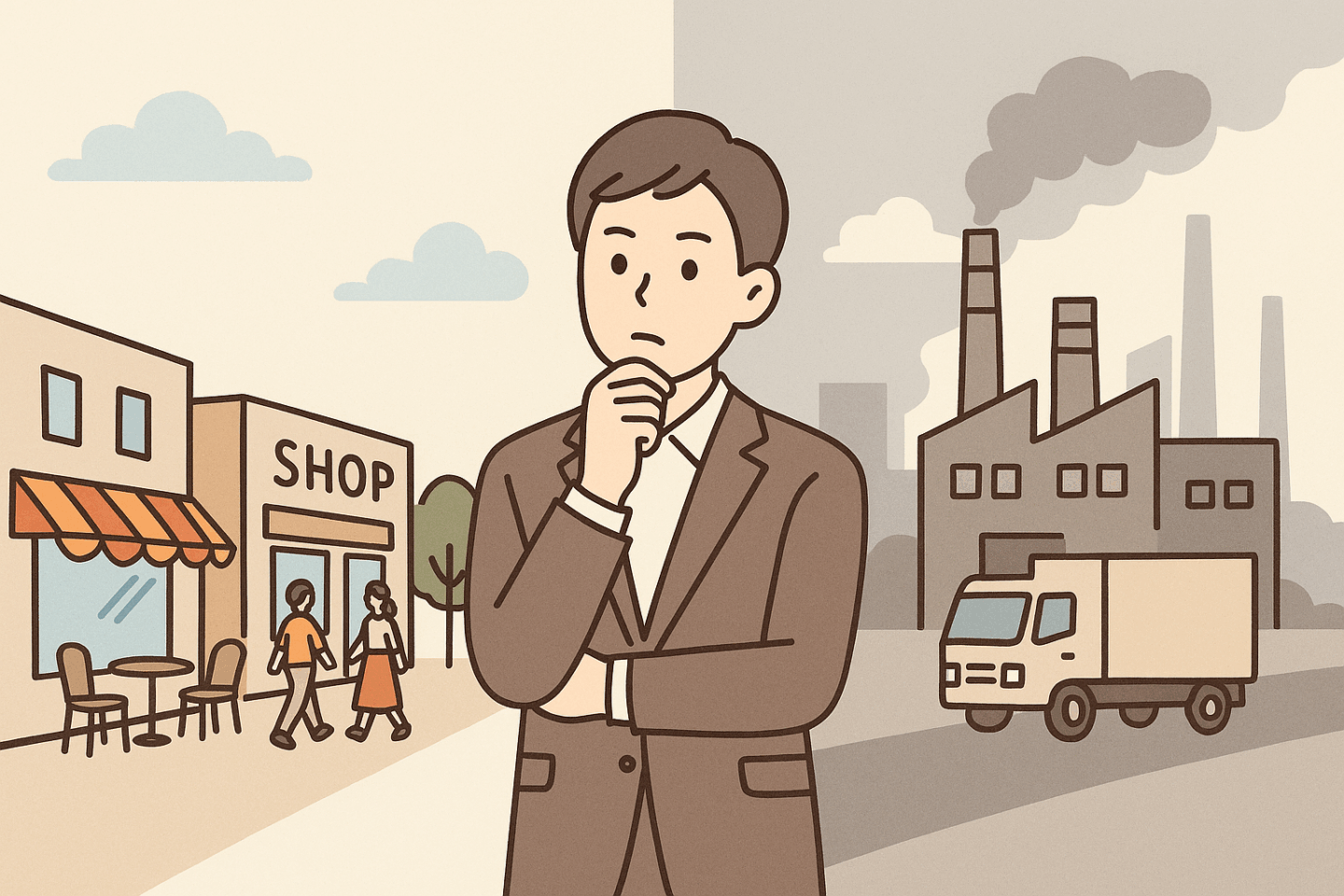
【大分】準工業地域の店舗探し完全ガイド!メリット・デメリット解説
準工業地域で店舗の開業を検討しているものの、具体的に建てられるものや、どのような制限があるのか分からずお困りではありませんか。
飲食店やコンビニは建てられますか?といった疑問や、そもそも店舗を建てられる面積、高さ制限など、専門的な情報が多くて混乱してしまいますよね。
また、準住居地域に店舗を建てられますか?という比較の視点や、住宅を併設する場合のメリット、デメリットも気になるところです。
インターネット上では「準工業地域はやめとけ」といった意見も見られ、後悔しないか不安になるかもしれません。
さらに、固定資産税がどうなるのかという現実的な問題もあります。
この記事では、準工業地域にできる具体例を交えながら、あなたの疑問や不安を一つひとつ解消していきます。
- 準工業地域に建てられる店舗の種類と具体例
- 店舗開業に関わる具体的な制限(面積・高さなど)
- 準工業地域で店舗を持つメリットとデメリット
- 後悔しないための店舗物件の選び方のポイント
準工業地域の店舗開業における基本情報
- 準工業地域には何を建てていいの?
- 準工業地域にできる具体例を紹介
- 飲食店やコンビニは建てられますか?
- 店舗を建てられる面積と高さ制限
- 準住居地域に店舗を建てられますか?
- 店舗併用住宅を建てるメリット
準工業地域には何を建てていいの?

準工業地域は、都市計画法で定められた13種類の用途地域の一つで、「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。
少し難しい言葉ですが、簡単に言うと「危険性の低い工場と、住宅や店舗などが混在できるエリア」のことです。
この地域は「何でもありの地域」と表現されることがあるほど、建てられる建物の種類が非常に幅広いのが最大の特徴です。
具体的には、以下のような建物を建てることができます。
準工業地域で建築可能な建物の例
- 住宅:戸建て、マンション、アパートなど
- 店舗・商業施設:飲食店、コンビニ、スーパー、床面積10,000㎡を超える大規模な商業施設など
- 事務所:オフィスビル
- 公共施設:学校(幼稚園から大学まで)、病院、保育所、図書館、神社仏閣など
- 遊戯施設:カラオケボックス、パチンコ店、映画館、ボーリング場など
- 宿泊施設:ホテル、旅館
- 工場:危険性や環境悪化の恐れが少ない、またはやや多い軽工業の工場、自動車修理工場など
このように、私たちの生活に関わるほとんどの建物を建てることが可能です。
一方で、どんなものでも建てられるわけではありません。
準工業地域で建築できない建物の例
- 危険性が大きい工場:火薬類を大量に扱う工場など、周辺環境に著しい悪影響を及ぼす可能性のある施設。
- 一部の風俗施設:個室付浴場型特殊営業(ソープランドなど)は建設が認められていません。
つまり、準工業地域は工業の利便性を図りつつも、住宅地としての側面も考慮されている、非常にバランスの取れたエリアであると言えるでしょう。
準工業地域にできる具体例を紹介
前述の通り、準工業地域では非常に多種多様な建物を建てられますが、ここではさらに具体的なイメージが湧くように、実際にどのような街並みが形成されるのか、その具体例を紹介します。
準工業地域の街並みは、昔ながらの町工場や職人街をイメージすると分かりやすいかもしれません。
小規模な工場が住宅と隣接して建ち並び、その近くに住民のための商店や飲食店がある、といった風景です。
しかし、近年では広い工場跡地などを利用して、新しい形の開発も進んでいます。
具体的な施設・店舗の例
- 大規模なショッピングモール:広い土地を確保しやすいため、大型スーパーや専門店、映画館などを併設した複合商業施設の建設が可能です。
- 高層マンション:容積率の制限が比較的緩やかなため、タワーマンションなどが建設されるケースもあります。
- ロードサイド店舗:幹線道路沿いに指定されることも多く、ファミリーレストラン、カーディーラー、家電量販店などの出店にも適しています。
- 物流倉庫・配送センター:工業地としての側面を活かし、ECサイトの拡大に伴い需要が高まっている物流関連施設の建設も盛んです。
- ホテルやレジャー施設:ボーリング場やゴルフ練習場など、広い敷地を必要とする施設も建設できます。
このように、準工業地域は「工場地帯」という一言では片付けられない、多様な顔を持つエリアなんです。
住宅、商業、工業という異なる要素が混在することで、独特の活気と利便性が生まれています。
他の用途地域と比較すると、その特徴はより明確になります。
| 用途地域 | 建てられる店舗の主な特徴 | 街並みのイメージ |
|---|---|---|
| 準工業地域 | 床面積の制限なく、ほとんどの店舗・施設が可能 | 工場、住宅、大規模商業施設が混在する多様な街 |
| 第一種住居地域 | 床面積3,000㎡以下の店舗・事務所・ホテル等 | 中高層マンションが中心の比較的落ち着いた住宅街 |
| 商業地域 | 工場以外のほとんどの建物が可能(日影規制なし) | 百貨店やオフィスビルが集中する都心部の繁華街 |
このように比較すると、準工業地域がいかに幅広い用途に対応できるエリアであるかがお分かりいただけるかと思います。
飲食店やコンビニは建てられますか?

結論から申し上げますと、準工業地域では飲食店やコンビニを問題なく建てることができます。
むしろ、他の用途地域に比べて制限が少なく、出店しやすいエリアの一つと言えるでしょう。
多くの用途地域、特に住居系の地域では、飲食店の開業にあたって床面積の合計に厳しい制限が設けられています。
例えば、「第一種中高層住居専用地域」では500㎡以下、「第二種中高層住居専用地域」では1,500㎡以下といった具体的な数値が定められています。
しかし、準工業地域には、このような店舗の床面積に関する制限がありません。
そのため、個人経営の小さなカフェから、ファミリーレストラン、さらには大規模な宴会場を持つ店舗まで、事業計画に合わせた自由な規模での出店が可能です。
深夜営業や風俗営業も可能
準工業地域は、深夜0時以降に酒類を提供する「深夜酒類提供飲食店」の営業も可能です。
また、スナックやキャバレーといった接待を伴う「風俗営業1号許可」が必要な店舗の営業も認められています。
これは、商業地域や近隣商業地域など、限られたエリアでしか許可されていない営業形態です。
もちろん、コンビニエンスストアの建設にも全く問題はありません。工場で働く人々や地域住民の双方からの需要が見込めるため、コンビニの立地としても適している場所が多いです。
幹線道路沿いであれば、ドライバーの利用も期待できるでしょう。
実は、準工業地域は多様な人々が集まるため、ターゲット設定次第では飲食店やコンビニにとって非常に魅力的な市場となり得るのです。
工場勤務者向けのボリューム満点の定食屋や、ファミリー層向けのレストランなど、地域の特性に合わせた店舗展開が成功のカギとなります。
店舗を建てられる面積と高さ制限

準工業地域で店舗を建てる際には、敷地に対してどれくらいの規模の建物を建てられるかを示す「建ぺい率」と「容積率」、そして建物の高さを制限するルールを理解しておく必要があります。
これらの制限は、他の用途地域と比較して緩やかに設定されているのが特徴です。
建ぺい率と容積率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合のことです。
この数値が大きいほど、敷地を広く使って建物を建てられます。
容積率とは、敷地面積に対する建物の延床面積(各階の床面積の合計)の割合を指します。
この数値が大きいほど、階数の多い、より大規模な建物を建てることが可能です。
準工業地域におけるこれらの数値は、都市計画によって以下のように定められています。
| 制限の種類 | 準工業地域で定められている数値 | 特徴 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50%・60%・80% のいずれか | 住居専用地域などと比べて上限値が高く、敷地を有効活用しやすい。 |
| 容積率 | 100%・150%・200%・300%・400%・500% のいずれか | 工業系用途地域の中では最も上限値が高く、多層階の建物を建てやすい。 |
これらの制限が緩やかであるため、準工業地域では敷地を最大限に活用した、比較的規模の大きな店舗やマンションの建設が可能になります。
高さに関する制限
住居系の地域に適用される「絶対高さ制限(10mまたは12mまで)」は、準工業地域にはありません。
ただし、無制限に高く建てられるわけではなく、周辺の住環境に配慮するためのいくつかのルールが存在します。
主な高さ関連の制限
- 道路斜線制限:道路の採光や通風を確保するため、道路に面した部分の建物の高さを制限します。
- 隣地斜線制限:隣の敷地の日当たりや風通しを確保するための高さ制限です。
- 日影規制(日影による中高層建築物の高さの制限):周辺の敷地に一定時間以上の日影ができないように、高さ10mを超える建物の形状を制限するルールです。
商業地域にはこの規制がありませんが、準工業地域には適用されるため、住環境が守られやすくなっています。
これらの規制があるため、高層の建物を建てる際には設計上の工夫が必要ですが、逆に言えば、周辺に建物が建つ場合でもある程度の日当たりは確保されるという安心感にも繋がります。
準住居地域に店舗を建てられますか?
はい、準住居地域でも店舗を建てることは可能です。
しかし、準工業地域とはその目的や制限の内容が異なります。
両者の違いを理解することは、物件選びのミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。
準住居地域は、「道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域」と定義されています。
その名の通り、幹線道路沿いに指定されることが多く、住宅と商業施設が混在するエリアです。
準住居地域と準工業地域の主な違い
一番大きな違いは、建てられる店舗の規模や種類です。
準住居地域はあくまで「住居の環境保護」も目的としているため、準工業地域ほど自由ではありません。
| 項目 | 準工業地域 | 準住居地域 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 軽工業の利便性向上 | 自動車関連施設と住居の調和 |
| 店舗の面積制限 | 原則なし | 床面積の合計が10,000㎡以下に限られる |
| 劇場・映画館 | 客席面積の制限なし | 客席面積が200㎡未満に限られる |
| 工場の建設 | 危険性が低いものであれば可能 | 原則としてごく小規模なもの(自動車修理工場などを除く)しか建てられない |
このように、準住居地域では大規模な商業施設や工場の建設が制限されています。
もしあなたが10,000㎡を超えるような大型店舗の開業を計画している場合、準住居地域は選択肢から外れることになります。
一方で、準住居地域は工業的な要素が少ないため、より住宅街に近い、落ち着いた環境で店舗を構えたい場合に適していると言えるでしょう。どちらの地域が良いかは、開業したい店舗の業種、規模、そしてターゲット顧客層によって大きく変わってきます。
店舗併用住宅を建てるメリット

準工業地域は、店舗だけでなく住宅も建てられるため、「店舗併用住宅」を建てる際の有力な候補地となります。
この地域ならではの特性を活かしたメリットがいくつか存在します。
準工業地域で店舗併用住宅を建てる主なメリット
- 高い利便性
- 土地価格のコストパフォーマンス
- 良好な日照条件
1. 高い利便性
最大のメリットは、生活の利便性が非常に高いことです。
前述の通り、準工業地域ではスーパーや病院、学校、レジャー施設まで、生活に必要なほとんどの施設を建てることが認められています。
そのため、職住近接を実現しながら、買い物や子育て、休日の娯楽まで、あらゆる面で便利な暮らしが期待できます。
幹線道路に近いケースも多く、車でのアクセスが良い点も魅力です。
2. 土地価格のコストパフォーマンス
一般的に、準工業地域の土地価格は、閑静な住宅街が広がる住居系の用途地域と比較して割安な傾向にあります。
これは、「工場が近くにあるかもしれない」というイメージから、純粋な居住目的での需要が住居系地域よりは低いためです。
しかし、実際には危険性の高い工場は建てられず、利便性はむしろ高い場合が多いため、「お得に広い土地を手に入れたい」「利便性を重視したい」と考える方にとっては、非常にコストパフォーマンスが良い選択肢となり得ます。
3. 良好な日照条件
「工業」という名前から日当たりの悪いイメージを持つかもしれませんが、実は日照条件が良い点も大きなメリットです。
準工業地域は、繁華街などに指定される商業地域とは異なり、「日影規制」の対象となります。
これは、周辺の住宅の日照を確保するためのルールであり、これにより建物が密集していても、ある程度の日当たりが保たれるようになっています。
店舗にとっても住宅にとっても、明るい空間を確保しやすいのは嬉しいポイントです。
失敗しない準工業地域の店舗の探し方
- 店舗併用住宅を建てるデメリット
- 準工業地域を選んで後悔する理由
- 「準工業地域はやめとけ」の真相
- 気になる固定資産税について
- 後悔しない準工業地域の店舗選び
店舗併用住宅を建てるデメリット

多くのメリットがある一方で、準工業地域に店舗併用住宅を建てる際には、事前に理解しておくべきデメリットも存在します。
これらを把握せずに計画を進めると、後々「こんなはずではなかった」と後悔につながる可能性があります。
準工業地域で店舗併用住宅を建てる主なデメリット
- 騒音・臭い・振動などの発生リスク
- 大型車両の通行とそれに伴う影響
- 周辺環境の変化の可能性
- 土壌汚染のリスク
騒音・臭い・振動などの発生リスク
準工業地域では、危険性の低い工場や作業場の建設が認められています。
そのため、隣接する敷地に工場が建った場合、機械の稼働音や作業に伴う振動、扱う製品によっては臭いが発生する可能性があります。
法的な基準はクリアしていても、静かな住環境を求める方にとってはストレスに感じることがあるかもしれません。
大型車両の通行とそれに伴う影響
工場や倉庫への資材搬入・製品搬出のため、トラックなどの大型車両が頻繁に通行することがあります。
これにより、交通量が増えるだけでなく、早朝や深夜の騒音、道路の傷みが懸念されます。
特に、小さなお子様がいるご家庭では、通学路の安全性について慎重な確認が必要です。
周辺環境の変化の可能性
準工業地域は、建てられる建物の種類が多いため、将来的に周辺環境が大きく変わる可能性があります。
現在、空き地や駐車場になっている土地に、数年後にはマンションや商業施設、あるいは工場が建設されることも十分に考えられます。
購入時には静かだった場所が、数年後には賑やか(あるいは騒々しく)なるリスクは考慮しておくべきでしょう。
土壌汚染のリスク
過去に工場や指定作業所があった土地の場合、有害物質による土壌汚染の可能性がゼロではありません。
見た目では判断できないため、土地の履歴を調べたり、必要に応じて専門家による土壌汚染調査を行ったりすることが安心につながります。
これは健康被害に直結する重要な問題です。
準工業地域を選んで後悔する理由
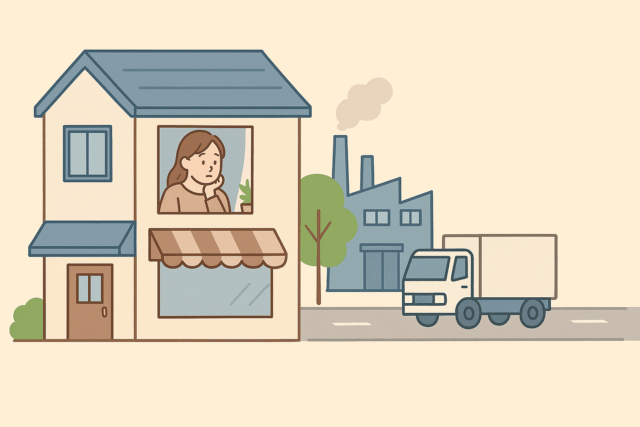
「準工業地域を選んで後悔した」という声は、主にデメリットとして挙げた要素を、購入前に十分に理解・確認していなかったケースで聞かれます。
具体的にどのような点で後悔しやすいのか、よくあるパターンを見ていきましょう。
後悔の最大の原因は、「住環境」と「事業環境」のミスマッチです。
ケース1:「静かな暮らし」を求めていた人の後悔
「土地が安くて利便性も高いから契約したけど、隣の工場の機械音が一日中聞こえてきて落ち着かない…。
窓も開けられないし、もっと静かな住宅街にすればよかった。」
これは、準工業地域を「少し賑やかな住宅街」程度に捉えてしまった場合に起こりがちな後悔です。
あくまで工業の利便性を目的としたエリアであるため、第一種低層住居専用地域のような静けさを期待すると、ギャップに苦しむことになります。
ケース2:子育て環境を重視していた人の後悔
「家の前の道路を大きなトラックが頻繁に通るので、子供を一人で遊びに行かせるのが怖い。
排気ガスも気になるし、公園も近くにない。子育てには向いていなかったかもしれない。」
交通量や周辺施設は、生活の質に直結します。
特に、歩行者の安全や空気の清浄さが求められる子育て世代にとっては、準工業地域の特性がデメリットとして大きく感じられる場合があります。
ケース3:将来の環境変化を予測していなかった人の後悔
「購入時は日当たりの良い角地だったのに。。。数年後に隣の空き地に高層マンションが建って、日中も真っ暗になってしまった。。。店舗の売上にも影響が出ている。」
周辺の空き地や古い建物の存在は、将来の環境変化リスクをはらんでいます。
用途地域の制限が緩い準工業地域では、その変化の振れ幅も大きくなる傾向にあります。
購入時の状況が永遠に続くわけではないという視点が不可欠です。
これらの後悔を避けるためには、現地調査を徹底することが何よりも重要です
。時間帯や曜日を変えて何度も訪れ、騒音のレベル、交通量、周辺住民の様子などを自分の目と耳で確かめる必要があります。
「準工業地域はやめとけ」の真相
インターネットで物件情報を検索していると、「準工業地域はやめとけ」という少し強い言葉を目にすることがあります。
これまで述べてきたデメリットを知ると、この意見がもっともらしく聞こえるかもしれません。
しかし、この言葉の真相は、「どのような目的で土地を探しているか」によって大きく変わってきます。
結論から言うと、「準工業地域はやめとけ」という意見は、「静かで落ち着いた住環境」を最優先事項として考えている人にとっての警鐘である場合がほとんどです。
一概に「やめとけ」と切り捨てるのは早計です。
準工業地域が、他のどの地域よりも最適な選択となるケースもたくさんあるんですよ。
「やめとけ」と言われる主な理由の再確認
- 工場の騒音や振動、臭いの可能性がある
- 大型トラックの通行が多く、安全面や環境面で懸念がある
- 多様な建物が混在するため、統一感のある街並みにはなりにくい
- 将来、周辺環境が大きく変わるリスクがある
これらの理由は、確かに住環境を第一に考える上では大きな懸念点です。
一方で、準工業地域が「おすすめ」になる人とは?
逆に、以下のような目的を持つ人にとっては、準工業地域は非常に魅力的な選択肢となります。
準工業地域が向いている人の例
-
- 店舗や事務所を併設したい事業者:建物の用途や規模の自由度が高く、ビジネスの可能性が広がります。
- コストを抑えて広い土地を手に入れたい人:住居系地域よりも割安な価格で、理想の広さの土地が見つかる可能性があります。
– 生活の利便性を最優先したい人:スーパーや飲食店、病院などが近隣に揃っていることが多く、快適な生活を送れます。
- 日中の騒音があまり気にならないライフスタイルの人:日中は仕事で外出していることが多いなど、住環境に対する価値観は人それぞれです。
つまり、「準工業地域はやめとけ」という言葉は、あくまで一つの側面から見た意見に過ぎません。
大切なのは、その言葉を鵜呑みにするのではなく、自分の目的やライフスタイルにその地域が合っているかどうかを、メリットとデメリットの両面から冷静に判断することです。
気になる固定資産税について
店舗や住宅を所有すると毎年かかってくるのが固定資産税です。
準工業地域の物件を選ぶ際、この税金が他の地域と比べてどうなるのかは、重要な関心事の一つでしょう。
固定資産税は、基本的に「課税標準額 × 税率(標準は1.4%)」で計算されます。
この課税標準額は、土地や家屋の評価額を基に算出されるため、物件の評価額がどうなるかがポイントになります。
準工業地域の土地評価額の傾向
一般的に、準工業地域の土地の評価額は、利便性の高い商業地域よりは安く、閑静な住居専用地域よりは高くなる傾向があります。
ただし、同じ準工業地域内でも、駅からの距離や道路付け、周辺の状況によって評価額は大きく異なります。
「工場が建てられる」という点が評価額を下げる要因になる一方で、「大規模な商業施設も建てられる」という点が評価額を上げる要因にもなるため、一概に「安い」あるいは「高い」とは言えません。
重要なのは「住宅用地の特例」
固定資産税額を大きく左右するのが「住宅用地の特例措置」です。
これは、人々が住むための住宅が建っている土地については、税金の負担を軽くするという制度です。
| 住宅用地の区分 | 課税標準額の軽減率 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分) | 評価額の 1/6 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 評価額の 1/3 |
注意すべきポイント
この特例は、あくまで「住宅」部分に適用されます。店舗併用住宅の場合、建物の構造や居住部分の割合によって、特例が適用される土地の面積が変わってきます。
また、工場や倉庫、店舗のみの土地として利用している場合は、この特例は適用されません。
そのため、同じ評価額の土地であっても、使い方によって固定資産税が何倍も変わる可能性があるのです。
購入を検討している物件の固定資産税が具体的にいくらになるかは、ケースバイケースです。
必ず不動産会社や市町村の担当課に確認し、事前にシミュレーションしておくことが重要ですよ。
後悔しない準工業地域の店舗選び
これまで解説してきたように、準工業地域は多くの可能性を秘めたエリアですが、その特性を理解せずに選ぶと後悔につながることもあります。
最後に、この記事の要点をまとめます。後悔しない店舗選びのために、ぜひ参考にしてください。
- 準工業地域は多様な建物が混在するエリア
- 危険性の高い工場は建設できない
- 飲食店やコンビニ、大規模商業施設も建設可能
- 建ぺい率や容積率の制限が比較的緩やか
- 店舗の床面積に関する制限が原則ない
- 土地価格が住居系地域に比べて割安な傾向にある
- 日影規制があり住環境にも一定の配慮がされている
- 騒音や振動、臭いなどのデメリットも存在する
- 大型車両の通行が多い場合があるため安全確認が必要
- 周辺環境が将来大きく変わるリスクを考慮する
- 「やめとけ」は住環境を最優先する場合の一意見
- 固定資産税は住宅用地の特例の有無で大きく変わる
- 準住居地域とは店舗の面積制限などで異なる
- 事前の現地調査が後悔を避ける最も重要な鍵
- メリットとデメリットを天秤にかけ総合的に判断する
- 専門的な知識が不可欠なためプロへの相談が成功への近道
準工業地域での店舗探しは、専門的な知識と多角的な視点が求められます。
ご自身のビジネスプランとライフプランに最適な物件を見つけるために、ぜひGMAネクストのような専門家にご相談ください。
このような不動産でお困りではありませんか?
- 大分市内に広大な工場跡地や事業用地、遊休地を所有している法人様
- 相続したが活用方法が分からず、管理にお困りの大規模な土地のオーナー様
- 専門的な知識が必要で、どこに相談すれば良いか分からない不動産の売却をお考えの方
- 資産価値を正しく評価し、好条件での売却を目指したい方
大規模な土地もまずはお気軽にご相談を|無料査定受付中
当社では、お客様が所有する不動産の価値を正確に把握するため、無料査定を実施しております。もちろん、ご相談内容については秘密を厳守いたします。
「売却するかは未定だが、まずは資産価値を知りたい」という段階でも構いません。大分市の不動産を知り尽くしたプロフェッショナルとして、お客様の状況に寄り添ったアドバイスをさせていただきます。
▶︎▶︎ お電話でのお問い合わせ:[電話番号]
097-552-0107